谷崎潤一郎の『卍』(1930年)は、複雑な人間関係と愛欲の葛藤を描いた長編小説。大阪を舞台に、男女の三角関係が織りなす心理劇が展開され、女性同士の愛情や嫉妬、裏切りが絡み合います。谷崎特有の美意識と官能性が際立つ作品で、伝統的な日本の美と近代的な情念が融合した物語です。語り手・園子の視点で描かれ、読者に真実と虚偽の曖昧さを見せる構造が特徴です。
以下、谷崎潤一郎の小説『卍』についての概要、あらすじ、感想、解説をお伝えします。
あらすじ
『卍』は、1928年から1930年にかけて「改造」誌に連載された谷崎潤一郎の作品で、大阪の上流階級を背景に、複雑な愛憎劇が展開します。物語は、主人公・園子(そのこ)の語り口で進行し、彼女が弁護士の夫・孝太郎(こうたろう)と、美術学校に通う美しい女性・光子(みつこ)、そして光子の恋人とされる綿貫(わたぬき)をめぐる四角関係が中心です。
物語は、園子が知人である「私」に、自身の体験を語る形式で始まります。園子は、夫・孝太郎との平凡な結婚生活に退屈していたところ、美術学校で出会った光子に強く惹かれます。光子は美貌と妖艶な魅力を持ち、園子は彼女に心を奪われ、親密な関係を築きます。しかし、光子には綿貫という恋人がおり、園子はこの関係に嫉妬心を抱きます。さらに、孝太郎も光子の魅力に引き込まれ、園子、孝太郎、光子、綿貫の四者による複雑な関係が形成されます。
光子は巧妙に三人を操り、園子と孝太郎の結婚生活は次第に崩壊していきます。園子は光子への愛と嫉妬、夫への不信感に苛まれ、孝太郎も光子への執着から抜け出せません。綿貫もまた、光子の本心を見極めようとしながら、彼女の策略に翻弄されます。物語は、光子が仕掛ける心理的な駆け引きと、四人の感情が錯綜する中で進行し、誰もが真実を見失い、破滅的な結末へと向かいます。
物語の終盤では、光子の真意が曖昧なまま、登場人物たちは互いに疑心暗鬼になり、関係は破綻します。園子の語り口は一貫しているものの、彼女の視点がどこまで信頼できるのか、読者に疑問を投げかける構造となっています。この曖昧さが、物語に深みを与え、谷崎の意図する「真実の不確かさ」を浮き彫りにします。
感想
『卍』を読了し、谷崎潤一郎の筆力と心理描写の巧妙さに深く感銘を受けました。本作は、単なる恋愛小説を超え、人間の欲望や嫉妬、信頼と裏切りの複雑な絡み合いを鮮やかに描き出しています。特に、光子のキャラクターは魅力的でありながら謎めいており、彼女の行動一つ一つが読者の好奇心を掻き立てます。園子の語り口は感情的で生々しく、彼女の視点を通じて物語を追うことで、読者は登場人物たちの心の動きに引き込まれます。
大阪の風土や文化が背景に描かれている点も印象的です。谷崎は、関西の上流階級の生活や、伝統的な日本の美意識を細やかに描写しつつ、近代的な情念や性愛のテーマを織り交ぜ、独特の雰囲気を醸し出しています。光子の美しさや、彼女が纏う着物の描写には、谷崎の美への執着が感じられ、官能的でありながらどこか冷ややかな印象を与えます。
また、物語の構造として、園子の語りがどこまで本当なのか、読者に委ねられる点が非常に興味深いと感じました。谷崎は、読者に「真実」をそのまま提示せず、登場人物の主観や偏見を通じて物語を構築することで、読み手自身に解釈を求める姿勢を見せています。この曖昧さが、読後の余韻を深くし、何度も読み返したくなる作品に仕上げています。
一方で、物語の結末にはある種の不完全さを感じました。光子の本心や、物語の全貌が明かされないまま終わるため、読者によっては消化不良に感じるかもしれません。しかし、この不完全さこそが、谷崎の意図するところであり、人間の関係や感情の複雑さを象徴しているように思えます。個人的には、この曖昧さが本作の魅力の一つだと感じ、谷崎の文学的技巧に改めて敬服しました。
解説
『卍』は、谷崎潤一郎の1920年代後期から1930年代初期にかけての作風を代表する作品であり、彼の美学やテーマが色濃く反映されています。谷崎は、伝統的な日本の美意識と西洋的な近代性を融合させることで知られ、本作でもその特徴が顕著に現れています。以下、作品の主要なテーマや構造について解説いたします。
愛と欲望の複雑性
『卍』の中心テーマは、愛と欲望が引き起こす人間関係の複雑さです。光子を中心とした四角関係は、単なる恋愛の三角形を超え、嫉妬、裏切り、支配と被支配の関係が絡み合います。光子は、男性と女性の双方を魅了する存在として描かれ、彼女の行動は計算的でありながら、どこか本能的でもあります。この二面性が、登場人物たちを翻弄し、物語に緊張感を与えています。谷崎は、愛情が純粋なものではなく、欲望やエゴイズムと不可分であることを強調し、人間の本性を赤裸々に暴き出します。
女性同士の関係
本作は、女性同士の愛情や親密さを描いた点で、当時の日本文学において先駆的な作品と言えます。園子と光子の関係は、単なる友情を超え、恋愛的な要素を含むものとして描かれますが、谷崎はこれを直接的に表現するのではなく、暗示的な描写で読者に委ねます。この曖昧さは、谷崎の他の作品(例:『春琴抄』)にも見られる特徴で、性愛や人間関係の多義性を強調しています。
語りの不確かさ
物語が園子の語り口で進行することは、谷崎の文学的技巧の重要な要素です。園子の視点は主観的であり、彼女の感情や偏見が物語の叙述に影響を与えます。これにより、読者は光子の行動や本心、さらには物語全体の「真実」を疑わざるを得ません。谷崎はこの構造を通じて、客観的な真実など存在しないという哲学的な問いを投げかけ、読者に解釈の自由を与えています。
大阪の風土と美意識
『卍』は、大阪の上流階級を舞台にしており、関西の文化や生活様式が細やかに描かれています。谷崎は、東京から大阪に移住した時期に本作を執筆しており、関西の風土や女性の美に対する独自の視点が反映されています。光子の着物や仕草、言葉遣いには、谷崎が愛した日本の伝統美が投影されており、官能的でありながらも洗練された美意識が感じられます。
谷崎文学の文脈
『卍』は、谷崎の創作における過渡期の作品と位置付けられます。彼の初期の西洋志向から、伝統的な日本の美への回帰が見られる時期に書かれた本作は、両者の融合が試みられています。また、谷崎の他の作品(『痴人の愛』や『春琴抄』)と同様、官能性や倒錯的な愛情、美的執着がテーマとして浮かび上がり、彼の文学的関心が一貫していることがわかります。
まとめ
谷崎潤一郎の『卍』は、愛と欲望、裏切りと嫉妬が絡み合う心理劇として、読者に深い思索を促す作品です。光子の謎めいた魅力と、園子の主観的な語りを通じて、谷崎は人間関係の複雑さと真実の曖昧さを描き出します。大阪の風土や美意識が織り交ぜられた本作は、谷崎の文学的技巧と美学が見事に結実した一作であり、現代の読者にも多くの示唆を与える名作です。

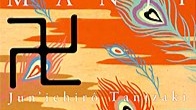


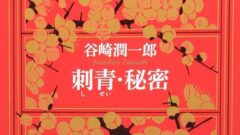
レビュー 作品の感想や女優への思い